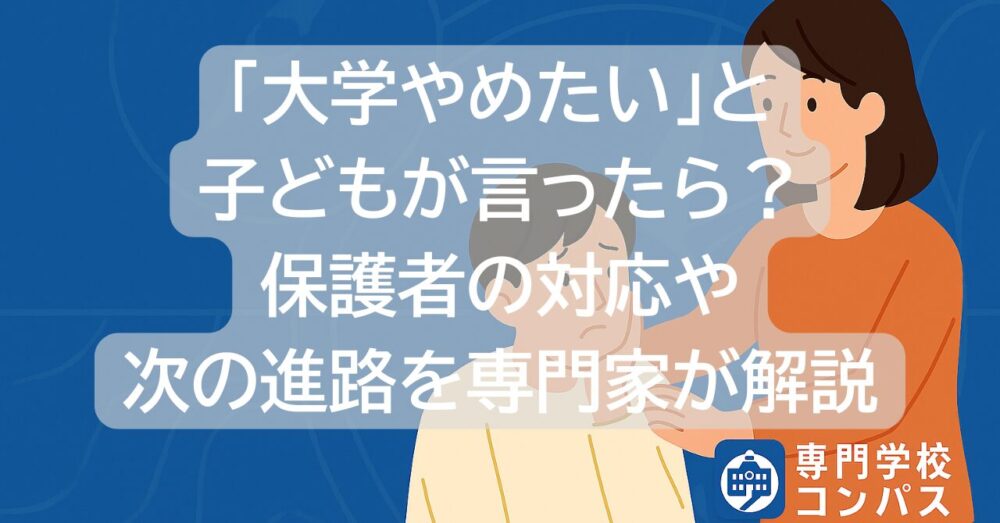「大学やめたい」とお子さんに言われたら、保護者としてはショックですよね。
こんな思いで頭がいっぱいになってしまうことでしょう。
- 「まさかうちの子が」という驚き
- 「どうにか続けられないの」という望み
- 「やめてどうするの」という不安
- 「せっかく入ったのに」「高い学費を払ったのに」という怒り
- 「つらい思いをしていたのかも」「早く気づいてあげれば」という切なさ
いったいどうすれば、と困惑してしまうのも無理のないことです。
「大学やめたい」とお子さんが言ったときの保護者の対応例や次の進路について書きました。
ぜひ参考になさってください。
「大学やめたい」は特殊なことなのか?
子どもが「大学やめたい」と言い出すことは、特殊なことではありません。
令和6年度の1年間に全国の大学生のうち50,516人が中退しています。
大学中退率は2%です。
また、同じく令和6年度1年間に全国の大学生のうち68,239人が休学しているのです。
大学休学率は2.7%ですね。
引用元:文部科学省 令和6年度 学生の中途退学者・休学者数の調査
また、高校によっては、進路指導で大学を強く勧められ、しぶしぶ納得させられて進学するケースもあるといわれていますので、これも「大学やめたい」の一因となっているかもしれません。
ですから、子どもが「大学やめたい」というのは、特殊なことではない、という点、また進路変更の原因が子どもだけのせいではないこともある点を理解しておきましょう。
落ち着いて子どもの話を聞きましょう
「大学やめたい」と子どもから打ち明けられた時は、こんなことに気を付けましょう。
- 頭越しに否定してはいけない。
- 話を途中で遮らない。
- 感情的な反応はしない。
- 子どもの話したいことはすべて話させる。
この時は子ども置かれた状況と、思っていることを正確に把握することに努めましょう。
正直に話をしてくれたということは、子どもも勇気を出したということです。
また、「今言ってくれてよかった」という受け止め方もできますね。
なぜ「大学やめたい」のか?ほかにやりたいことがあるのか?
子どもの話をすべて聞いたら、「大学やめたい」の一番大きな原因を明らかにしましょう。
「大学やめたい」の原因には次のような内容がよく見られます。
- 授業に関すること
授業が難しい
思った学習内容と違う
- 人間関係
友達ができず孤立している
友人とのトラブル
サークルでの人間関係に悩んでいる
大学やアルバイト先での金銭トラブル
- 将来への不安
進級や卒業への不安
就職への不安
- 進路決定時の間違い
そもそも大学へ行きたくなかった
行きたい大学ではないため気力を喪失
本当は別の進路に進みたかった
子どもが「大学やめたい」と思う原因を理解してあげて、一緒に気持ちを整理してあげることが大切です。
保護者には深刻なことではないように感じられても、子どもは「大学やめたい」と思い詰めているのですから。
保護者がその原因を理解してあげることで、子ども自身も幾分落ち着くことでしょう。
こうして保護者も子どもも落ち着いた時点で、これからどうする、ということを考えるのがよいでしょう。
このとき、子どもの精神的負担やメンタルの状況には細心の注意を払いましょう。
カウンセリングや学生相談室の利用もひとつの解決手段になることがあります。
続ける方法はないのか?
「大学やめたい」の原因がはっきりしたところで、これからどうするか、ということを考えましょう。
原因に対処して、解決できるのであれば、それに越したことはありませんね。
もう一度、気を取り直して大学生活を送り、卒業、就職を目指してもらうのが、保護者としてはなによりでしょう。
子どもは思い詰めています。
ですから、保護者が一緒になって考えてあげることで、落ち着かせてあげましょう。
保護者に相談したことがきっかけとなって、原因を解決しようとする意欲が生まれてくることもありますからね。
また、すぐに大学生活を元通りにするのが難しいようであれば、休学する、という手もあります。
時間を取って、落ち着いてから、気分を新たに再スタートするつもりで大学を卒業するのも、有効な手段だと思います。
就職にあたっても、大学を5年、6年かけて卒業した、というのは致命傷となることは、あまり考えられませんよ。
休学する、しないは違いますが、「大学やめたい」と思っていた子どもが、無事に卒業、就職してくれるのが保護者としては一番安心できますよね。
大学をやめたあとの進路は?
さて、「大学やめたい」の原因がハッキリして、話をしてみたけれど、やっぱり「大学やめたい」という意思が変わらなかった場合は、どのような進路があるのでしょうか。
大学をやめたあとのおもな進路は次の3つです。
それぞれにメリット・デメリットがありますので解説しますね。
別の大学に進学する
これは「大学やめたい」の原因が「行きたい大学ではないため気力を喪失」の場合に特に有効な進路です。
メリット:気力を取り戻して充実した大学生活を送れる可能性が高い。
デメリット:高等教育の修学支援新制度、日本学生支援機構の給付型奨学金は利用できない。(日本学生支援機構の貸与型奨学金は利用できる可能性あり)
このケースでは、就職活動においても一度大学を辞めたことについては、ポジティブに説明することができますので、心配はないと考えられます。
専門学校に進学する
この進路は、将来の職業について具体的な業務内容を明確にイメージできる場合に有効なものと言えるでしょう。
メリット:実際に携わる業務内容によって就職することができる。
デメリット:高等教育の修学支援新制度、日本学生支援機構の給付型奨学金は利用できない。(日本学生支援機構の貸与型奨学金は利用できる可能性あり)
大企業、上場企業への就職には不利。
高卒で就職する(他の学校には進学しない)
この進路は、上のふたつの選択肢に比べるとメリットは少ないと言わざるをえませんね。
メリット:追加の学費がかからず、早く社会に出て経験を積むことができる。
デメリット:高卒就職の時期ではないので、就職先が限定される。
いずれのケースでも、今までに費やした時間と費用は失われることになります。
しかし、子どもの年齢を考えると、十分取り返せる範囲だと思います。
キャリア再設計と捉えるのもポジティブでよいでしょう。
のちに、「あの時大学やめたけど、結果はよかったね」と言えるようにすることが大切ですね。
子どもの意思を尊重しながら決定しましょう
このあと、どうするのか、次の進路について説明しましょう。
決定にあたっては、子どもの意思を尊重するよう心掛けてください。
もちろん、保護者の意見を伝えることは大切ですが、それをもとにした子ども本人の意思が最も大切です。
高校卒業時点の決定をやり直すことになるわけですから、今回は言い訳できません。
あとで、「あの時〇〇がこう言ったから」とお子さんが思わないようにしてあげることが大切でしょう。
今後の進路のための計画を立てましょう
大学に残る決定の場合には、特に準備は必要ありませんね。
張り切って大学に通うだけです。
大学をやめて進路を変更する場合には準備をする必要があります。
1:大学をやめる手続き
大学の退学手続き:大学をやめるにあたっては、在籍する大学の規定にしたがって所定の手続きをする必要があります。退学願、退学届等の必要書類を準備して、学生証とともに教務課に提出する、というケースが多いようです。詳しくは在籍大学で調べましょう。
奨学金手続き:日本学生支援機構の給付型・貸与型の奨学金を受けていた場合には日本学生支援機構で手続きをする必要があります。
参考に日本学生支援機構の公式サイトの記述を引用します。
手続き方法
- 1.学校担当者に連絡し、奨学金の振込を止めてもらう。
※奨学生の資格がなくなった後に振り込まれた奨学金は、学校の指示に従い、すみやかに金融機関を通じて機構に返金してください。 - 2.「異動願(届)」を学校から受け取り、必要事項を記入し学校へ提出する。
- 3.<貸与奨学金>「貸与奨学金返還確認票」を学校から受け取り、内容を確認する。住所等に変更がある場合は、スカラネット・パーソナルから変更する。
- 4.<貸与奨学金>口座振替(リレー口座)加入手続を行う。
引用元:日本学生支援機構公式サイト
大学の寮に入居している場合:大学の学務課等で退寮手続きをした後、転居する。
一人暮らしで賃貸マンションに住んでいる場合:賃貸契約を結んでいる不動産会社に連絡して退去手続きをしたあと、転居する。
2:次の進学先を探す
別の大学または専門学校に進学することを決めた場合には、進学先を探す必要があります。
前回の進学先選びを教訓にして、じっくり選びましょう。
3:就職先を探す
高校卒業時に就職するのと違い、高等学校の求人斡旋は受けられません。
求人情報を自ら集める必要があります。
ハローワークインターネットサービスや民間の求人情報サイトを利用して求人情報を集めましょう。
ハローワークの求人情報を見るときには、求人票の「学歴」欄に注意してください。「学歴不問」となっていれば応募可能です。
大学をやめたときには、次の進路に進むために、以上のような行動が必要です。
これらを計画的に進めましょう。
新たな計画の実行をサポートしていきましょう
子どもが進路を決定したら、先のような行動を計画的に進めるためのサポートが保護者の方の役割でしょう。
主役はあくまで子どもですが、子どもの行動や精神状態をよく見ながら、適切な声掛けをして差し上げてください。
口出ししすぎもNGですが、放置するのもいけません。
最初の進学の時以上に注意を払ってあげましょう。
「大学やめたい」と子どもが言ったら?保護者の対応や次の進路を専門家が解説 まとめ
「大学やめたい」とお子さんが言ったら保護者のあなたはさぞ、驚かれることでしょう。
しかし令和6年度の1年間には大学生のうち50,516人が退学しています。
大学中退率は2%です。
また268,239人が休学しており、大学休学率は2.7%です。
あなたのお子さんが決して特殊なのではありません。
どのご家庭にも起こりうることと言えるでしょう。
そんな時に「大学やめたい」と聞いた保護者が、一緒に感情的になってはいけません。
保護者としては驚き、怒り、不安、切なさなどを感じるでしょうが、まずは落ち着いてお子さんの言うことをすべて聞いてあげることが大事です。
お子さんが「大学やめたい」と思う原因を明確にして、大学を続けることはできないのか、可能性を探りましょう。
続けることができないようであれば、次の進路の可能性を考える必要がありますね。
この記事では「別の大学に進学」「専門学校進学」「高卒で就職」の3つのケースについてご紹介しました。
保護者の思いもおありでしょうが、次の進路の決定はお子さん本人の意思を尊重して差し上げましょう。
決定したら、保護者としては次の進路にむけて必要な行動を計画的に進めるよう見守りながらサポートに徹してくださいね。
「大学やめたい」と思い詰めているお子さんとその保護者の方の悩みの解決に役立つよう願います。
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。